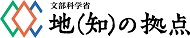
≪地域学 本科5年生 一般選択≫
地方創生推進事業(COC+)の一環として、本科5年生において地域創生理解科目の「地域学」が、平成31年4月9日(火)より全14回に渡って進められております。
本講義は、グローバリゼーションの進展と地域への影響や持続可能な地域の発展の重要性を理解し、地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)とその機能について"工学的な知識をもつ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか"について学び、グループワークを通じて実際に場所・地域をイノベーションするためのプランを構想することで、学生は世界の中で、地域をイノベーションしていくことの重要性を共有して参ります。
今後、地域産業・経済をテーマに、期間中の授業において、実際に地方創生や起業の経験を有する者による特別講演を予定しております。
≪地域学 講義項目・内容(予定)≫
| 週数 |
日程 |
講義内容 |
| 第 1週 |
4 /9(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
ガイダンス |
| 第 2週 |
4 /16(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
グローバリゼーションの展開 |
| 第 3週 |
4 /23(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
グローバリゼーションと地域 |
| 第 4週 |
5 /7(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
地域の持続可能な発展の重要性 |
| 第 5週 |
5 /14(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
「主権者として税を考えよう」
特別講師:図司税理士事務所 図司皓一税理士
|
| 第 6週 |
5 /21(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
奈良県の地理的・経済的特徴
吉野林業の概観
|
| 第 7週 |
5 /28(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
「木のまち吉野の取り組みについて」
特別講師:吉野町 産業振興課 木のまち推進室 椿本久志室長
吉野中央木材株式会社 石橋輝一専務取締役
|
| 第 8週 |
6 /11(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
地域社会の担い手
地域の課題解決における技術者の重要性
|
| 第 9週 |
6 /18(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
グループ演習(1) |
| 第10週 |
6 /25(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
グループ演習(2) |
| 第11週 |
7/ 2(火)
3-4限目(10時40分~12時15分)
|
グループ演習(3) |
| 第12週 |
7 /9(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
「間伐材イノベーションで林業振興を目指す取り組み」
~おがくず化、そして最先端のバイオマス素材への活用~
特別講師:奈良高専 物質化学工学科 中村秀美教授
|
| 第13週 |
7 /23(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
最終発表 |
| 第14週 |
7 /30(火)
3-4限目(10時40分~12時15分) |
振り返り |
≪地域学 担当 竹原信也 准教授 ≫

第12週 特別講義 奈良高専 物質化学工学科 中村秀美教授
「間伐材イノベーションで林業振興を目指す取り組み」~おがくず化、そして最先端のバイオマス素材への活用~
2019年7月9日(火)本校地域創生交流室において、本校物質化学工学科 中村秀美教授による第12回『地域学』(担当教員:竹原准教授)の特別講義が行われました。
今年度前期の『地域学』では、奈良県の重要課題の一つである林業の復興にスポットを当て、その事例として、吉野町の製材業を題材に、同町の活性化と地域のグローバリゼーションについて受講生が考察を重ねてきました。
中村教授は、現在、本校が地域創生推進事業(COC+)の一環として取り組んでいる地域共創研究クラスターの一つである「環境クラスター」のリーダーとして、木材を主原料とする最先端バイオマス素材であるセルロースナノファイバー(CNF)の研究開発に取り組んでおり、本研究テーマは、平成30年度より学内で新設された「奈良高専特色研究※」の採択テーマともなり、注目を集めております。
|

(竹原准教授による中村教授の紹介)
|

(物質化学工学科 中村教授)
|
今回の講義では、中村教授が取り組むCNFを用いた複合化プラスチックの開発を中心に、実用化に向けた課題や将来的な展望について講義が行われ、CNFを糸口に、奈良県の豊かな森林資源を背景とした木材の活用拡大への期待と熱い思いを受講生に伝えていただきました。
|

(講義の様子)
|

(質疑応答の様子)
|
受講生たちは、今回の講義を通じ、奈良県の重要課題である林業の復興において、木材利用の用途拡大の重要性や最先端研究であるCNFの秘めた可能性を知ることで、木材への関心を高めるよい機会となりました。
※「奈良高専特色研究」とは、学内の独自制度として平成30年度よりスタートした制度で、特に社会のニーズに応えた研究テーマを学校あげて重点的に支援し、広く地域社会への研究成果の還元を目的としたものです。
≪地域学 担当 竹原信也 准教授 ≫

第7週 特別講義 吉野町産業振興課木のまち推進室 椿本室長、吉野中央木材株式会社 石橋専務
「木のまち吉野」の取り組みについて
2019年5月28日(火)、本校地域創生交流室において、吉野町 産業振興課 木のまち推進室 室長 椿本久志氏、吉野中央木材株式会社 専務取締役 石橋輝一氏による第7回『地域学』の特別講義が行われました。
冒頭、担当教員 竹原准教授から講師の紹介があり、その後、「木のまち吉野の取り組みについて」と題して、講義がはじまりました。
講義の前半は、吉野町 産業振興課 木のまち推進室 椿本室長による吉野町の"木"に関する取り組みの話です。はじめに吉野町について概要説明があり、その後、吉野の山と木について、吉野貯木場の歴史、吉野材用途の変遷、活性化に向けた取り組み等について紹介がありました。吉野町の主要産業である木材関連産業は、安価な外国産木材とのコスト競争による価格低下や人手不足に伴う後継者問題など取り巻く環境が厳しさを増す中、活性化に向け取り組んでいる様々な施策につき実例を交え紹介がありました。
また、地元で"木"に携わる人たちが登場する吉野町のPR動画も披露いただき、現地を見学している雰囲気の中で、吉野町の人たちの思いが伝わってきました。
講義の後半は、現地で製材業に従事する事業者の立場から吉野中央木材株式会社 石橋専務による講義です。
1本1本の木を大切に使い切る日々の仕事の積み重ねを通じて吉野の山の持続的な循環を支えていくという信念で「木と暮らす」提案を続けている会社のポリシーについて紹介があり、その後、平成28年度から吉野町で取り組んでいる「木とのふれあいイベント」や「木育の推進」など様々な施策について紹介がありました。
|

(講師紹介の様子)
|

(吉野町役場 椿本 久志氏)
|
 |
 |
| (椿本室長による講義の様子) |
|

(石橋専務による講義の様子)
|

(質疑応答の様子)
|
最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生の質問に対し、丁寧に返答いただきました。
本講義を通じて、吉野町と"木"の強い結びつきを知ると共に、講義の最後に示された今後の吉野町の課題に対し、学生の意識を高めることができました。
≪地域学 担当 竹原信也 准教授 ≫

令和元年5月14日(火)、本校地域創生交流室において、図司税理士事務所 税理士 図司皓一氏による第5回『地域学』の特別講義が行われました。
冒頭、担当教員 竹原准教授から図司皓一氏の紹介があり、その後、「責任ある社会の一員として自立して生きるために主権者として税を考えよう」と題して、図司氏の講義がはじまりました。
現在、日本には約50種類の税があり、その中でも特に身近な「消費税」「所得税」についてそのしくみからわかりやすく説明がありました。公平な税負担の考え方、問題点など事例を交え学びました。
また、将来の起業を目指すための基礎知識として法人税のしくみ、国の税金の使い道や奈良県の財政等について幅広く説明がありました。
第5週 特別講義 図司皓一氏(図司税理士事務所)
奈良県の地域経済【1】 「主権者として税を考えよう」
|

(講師紹介の様子)
|

(図司皓一氏挨拶の様子)
|
 |
 |
| (講義の様子) |
|

(グループワークの説明の様子)
|

(グループワークの様子)
|
講義終盤には、奈良県の税収を記したワークシートが配られ「税収から考える奈良県の特徴と課題」と題したグループワークをおこない、税収から見えてくる奈良県の特徴や京都府と比較した場合の奈良県の課題、またその課題への対策等につき受講生が自身の考えをまとめました。
最後に、講義の締めくくりとして、税金を納める意義について説明があり、国民の義務である納税について正しい知識を得るとともに、財政面から奈良県の課題を考えるよい機会となりました。