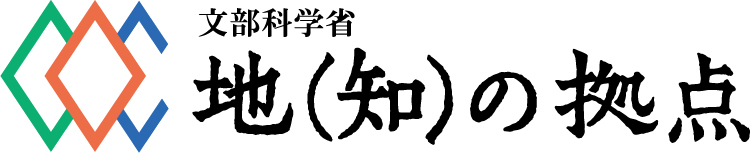
3月15日(火) 本校 谷口校長、地方創生研究センター長 早川教授が社会福祉法人天寿会特別養護老人ホームひびきの郷 様を訪問し、理事長 林 芳繁様との対談が行われました。
天寿会様は介護・福祉事業において、時代の変化に即応した総合サービスの提供に努めながら、地域ぐるみで安定した暮らしを支える拠点となる県内の有力機関です。本校とは10年前から「介護ロボット」の開発において密接な協力関係にあり、地方創生推進事業(COC+)の事業協働機関として参画頂いております。

( 早川教授 ・ 谷口校長 ・ 林 理事長 )
【谷口校長】
お忙しい中、貴重なお時間を頂戴しありがとうございます。
天寿会様とは「介護ロボット」の開発に向け連携した取り組みを推進中であり、これまで取り組まれてきたご経験や介護・福祉分野の現状などをお聞かせ頂ければありがたいです。
【林理事長】「音楽一筋から音楽と福祉の道を歩む人生となり、音楽の鳴りひびく館、『天寿会ひびきの郷』を創設しました」
若い頃から音楽の道に携わり、フランス政府給費留学生として海外生活も経験致しました。帰国後、大学で音楽を教えながら、これから迎える高齢化社会を考え30年程前に音楽でリハビリをとの想いで、「音楽と福祉」の道を歩むことにしました。“音楽の鳴りひびく館“という想いを込めて「ひびきの郷」と命名し社会福祉法人天寿会を創設しました。
【谷口校長】
介護現場では色々な苦労があるかと思います。
【林理事長】「10年前から介護の現場にロボットを導入していれば、今の介護・医療はもっとよくなっていたと思います」
|
実際の現場で仕事を続けていると、介護に携わる人の体力的な負担が大きいということがわかりました。要介護高齢者向けの介護用具は色々開発されておりますが、介護する職員向けのものはほとんど考えられていないのが現状です。そこで、介護する人たちの負荷を軽減する介護補助ロボットのようなものができないか、と言う思いが募り10年前に奈良高専の先生に相談を持ちかけたのがお付き合いの始まりでした。
当初は、学生の手作りのような「背負い式介護ロボット」を東京ビックサイト・ロボット博へ出展しました。昨年4月にインテックス大阪バリアフリー展・ロボット博に、再び奈良高専と「背負い式介護ロボットひびき号」を出展しました。これは、機器製造の技術を有するテクノス株式会社様にも加わって頂き、奈良高専との共同研究成果として発表するに至りました。苦節10年の思いは昨年11月に行われた東京ビックサイト・ロボット博2度目の出展で、改良を加えた「背負い式介護ロボットひびき号」で多くの方から絶賛を頂きました。また、早川教授と県下の大学で介護ロボットに関する講演も行い、介護に携わる人の負荷軽減の重要性を訴えてきました。 |

(背負い式介護ロボットひびき号)
|
【谷口校長】
今後、介護はどのような方向に進んでいくと思われますか。
【林理事長】「社会福祉法人は地域包括ケアで社会貢献していきます」
厳しい財政状態にある日本では、社会福祉法人も改革を迫られております。社会福祉法人が医療との連携・地域との連携による地域包括ケアで、介護保険財政の持続可能性にどれだけ貢献できるかが一つの課題です。社会福祉事業を取り巻く環境は大幅に変化しております。営利法人等と非営利法人とが共存し、同種のサービスを提供する特殊な環境です。サービスの質・利用者の利便性が高まるよう経営主体間のイコールフッティング(双方が対等の立場で競争が行えるように、基盤・条件を同一にすることなど)の確立が求められています。非営利法人だからこそ目指すべきは社会貢献だと思っております。これからは、施設に入居するのではなく、地域で支援が受けられる生活介護支援サポーター、ボランティア等の役割が重要になってくると思います。「この町で住んで良かった。」「この町でいつまでも住み続けたい。」そして「この町で地域の方々に看取られて旅立っていきたい。」このような、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるような町づくり、在宅介護のニーズは益々大きくなってくるでしょう。
【谷口校長】
いま特にどのようなことに力を入れられておられますか。
【林理事長】「誰もが住んで良し、健やかに暮らせる地域づくりを目指しています」
|
他の先進国に例を見ないスピードで進行している日本の少子高齢化ですが、奈良県においても例外ではありません。人口構造がつぼ型に変化していく中であっても、“誰もが住んで良し、健やかに暮らせる地域づくり”に関心があります。業界へ先駆けて取り組む「音楽療法」や「和薬膳料理」の導入、趣味や特技を活かした「クラブ活動」、四季折々を楽しむ「フェスタひびきの郷」で地域や家族との交流により実現しております。また、国庫補助金事業を受託しモデル事業として奈良県で初めてとなる「安心生活創造事業」・「ふれあいサロン」を開設しました。買い物支援や病院の付添い支援など高齢者の見守り事業を始めました。
|
 |
【谷口校長】
我々の世代になってくると益々介護が受けられないケースが増えてきそうですね。
【林理事長】「奈良県がリードしてロボット製作・普及に力を入れてもらいたいです」
少子高齢化が進み、介護の需要と供給が益々アンバランスになり、高齢者受難の時代がすぐそばに迫っております。その為にも介護を補助する「介護ロボット」の本格的な普及を急ぐ必要があると感じております。奈良県がリードしてロボット製作に力を入れ予算をつけて普及につとめてもらいたいです。今後も奈良高専と連携し、ロボット開発に積極的に取り組んでいきたいと思います。
【谷口校長】
音楽療法の効き目について、もう少しお聞きできればありがたいです。
【林理事長】「音楽療法には、症状を穏やかにしてくれる効果があります」
|
アメリカには、米国認定音楽療法士の資格があります。近年では音楽療法士の資格を認める州が増えてきています。日本には、理学療法士や作業療法士など色々な資格がありますが、現在のところ「音楽療法士」の国家資格は、残念ながらありません。
認知症は早期発見が重要です。「まだ食事をしていない」「あなたどなた」など人・とき・場所などがわからなくなります。しかし、昔のことは想い出します。歌は、聞いたその時のことを思い起こしてくれます。例えば、「うみ」の歌を聞けば、海に行った頃のことを思い出します。尊厳ある生活を保つためには、右脳の前頭葉を刺激する必要があります。歌や楽器、懐かしい童謡や流行歌を聞いて、今まで笑わなかった人が笑いながら口ずさんだりします。音楽療法には、症状を穏やかにしてくれる効果があります。当施設には認知症の方もたくさんおられますが、週末演奏会や毎月ミュージックセラピーを実施し音楽によるリハビリを続けていることもあって、施設内を徘徊する人はほとんどいません。
高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭「ねんりんピック」が毎年開催され、その中で世代間・地域間交流を図る目的で音楽文化祭も行われています。
|
 |
【谷口校長】
施設内で実施されている音楽療法では具体的にどのようなことをされていますか。
【林理事長】「音楽で、心と心のブリッジをつなぎ、心と心が響き合います」
|
人と人との「心のつながり」が大切です。歌を歌いながらお互いの目と目を見ながら手と手でバチを持ちます。バチが橋となり、“心と心のブリッジをつなぐ“ことが出来ます。また、演奏に合わせて太鼓をバチでたたいてもらうと、始めはリズムが合わなくてもたたいているうちに、脈や呼吸に合わせて太鼓の音も合ってきます。打楽器による音色は、安心感を持たせてくれるのです。
疲れてしまわないように、30分程度を目安にあまり長時間にならないように行っております。
|
 |
【谷口校長】
介護現場での人手不足についても苦労されているかと思います。
【林理事長】「介護の人手不足解消として優秀な外国人に日本に来て学んでもらい、資格を取って帰国してもらうグローバル人材育成『EPA介護福祉士養成』に現在は、取り組んでいます」
将来的には介護現場の人手解消手段として「介護ロボット」に期待するところですが、現在は、外国人に期待する部分が多いです。厚生労働省の技能実習制度を採り入れ、今後は、開発途上国等の外国人を一定期間(最長3年間)受け入れ、現場で実務を行うことにより技能を身につけ、母国に帰って活躍してもらうことに取組んでいます。国内の人手不足解消だけでなく開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力していきたいと思っております。実際、当施設には、インドネシア・ベトナムなどから10名程の外国人が介護現場で働いております。彼らは総じて勤勉・勤務態度もまじめで、施設に貢献してくれております。
【谷口校長】
豊富な海外ご経験が積極的な外国人受け入れに繋がっているのかとご推察いたします。
【林理事長】「常に、人は人のためになる人になれと言う思いを胸に抱いています」
私の信念として、「人は人のためになる人になれ」と言う思いを何より大切にしております。
私自身、ロータリークラブに所属し、例えば、タイの小学校に浄水器を寄贈したり、病院に透析器を贈呈したり、国内外を問わず「人のため」になることを心掛けております。
【谷口校長】
今後も天寿会様と連携を密にして引き続き「介護ロボット」の開発に邁進し、介護現場での課題克服に寄与していければと思います。本日は本当にありがとうございました。

※今後も天寿会様とは、介護・福祉分野で直面する色々な課題の解決に向け連携を深めていくことを確認し合い、和やかに対談を終えました。
対談終了後、施設内を見学させて頂き、施設内の取り組みを体感させて頂きました。広く海外から人材を登用されている天寿会様には、たくさんの外国人職員がおられ、そういった方々と奈良高専の学生や留学生との交流・意見交換の場を設けていくことでグローバルな視点での発想が互いに生まれれば今後の介護現場でのテーマ発掘につながると感じました。