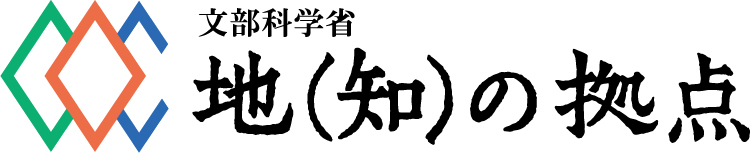
3月10日(木)社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 院長 瀬川 雅数様、管理部次長
松井 孝安様が来校され、本校 谷口校長、地方創生研究センター長 早川教授、情報工学科 上野講師との対談が行われました。
済生会奈良病院様と本校は、現在、医療情報システム開発の共同研究を進めており、県内の有力医療機関として本校の地方創生事業(COC+)へ事業協働機関として参画頂いております。今後も本校の地域共創研究クラスターにおける医工連携を推し進めていく上で済生会奈良病院様との連携を深めていくことを確認し合いました。
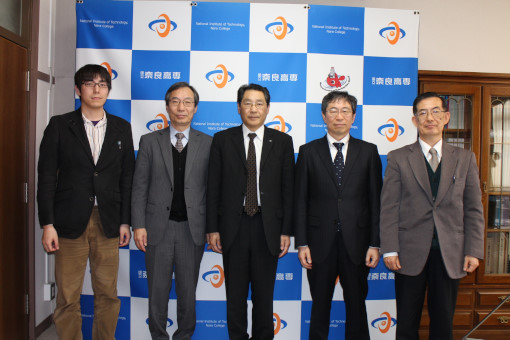
( 上野講師 ・ 谷口校長 ・ 瀬川院長 ・ 松井管理部次長 ・ 早川教授 )
【谷口校長】
本日はお忙しい中、お越し頂きありがとうございます。
|
【瀬川院長】「医療と介護で暮らしを支える」
現在、奈良高専とは共同で要介護者見守りシステムの開発に取り組んでおり、担当の先生方とは頻繁にコミュニケーションをとっております。
当院では、平成27年度に「地域包括ケア病棟」を開設し、効率的でかつ密度の高い医療を行うための施設基準の下、入院治療後に病状が安定した患者様に対して、在宅・生活復帰を目指した支援を行っております。
|
 |
【松井管理部次長】「専門分野の異なる人たちが集まり、交流を深める多職種連携が重要です」
地域包括ケアにおいて当院では、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護サービス、ケアマネージャー、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー、その他メディカルスタッフといった各種専門職の人たちが協力して在宅復帰支援に取り組む必要があります。そういった専門分野の異なる人たちの多職種連携がどのように効果的に機能するかが重要です。
多職種連携を始めた当初は、特に介護に携わる人たちから見れば医療に携わる人たちとの連携は、なかなか敷居が高いと思われていました。交流を深めるうちにコミュニケーションをはかり、連携も深めていくことができるようになりました。

( 多職種による事例検討会を2カ月に1回開催しています )
【谷口校長】
一言に地域包括ケアといっても色々な課題があるかと思います。
【松井管理部次長】「地域包括ケアには各種専門職に加えて、住民の参加が必要です」
地域包括ケアでは、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的なシステムの提供が不可欠です。各種専門職の密接な連携と共に、患者様やご家族の正しい理解やその地域性にあったシステムづくりが必要です。このご当地システムづくりには、その地域に住む住民の参加が必要です。住民も重要な連携メンバーの一員なのです。そのため住民に地域包括ケアの理解を深めて頂く取り組みの一つとして「退院が決まったら」と題し、各種専門職の人たちによる寸劇を開催しました。退院後も安心して暮らせるよう、在宅でどのような医療・介護サービスが使えるかを、専門職の立場から説明しています。

( 奈良県立図書情報館での各種専門職による寸劇 )
【瀬川院長】「多職種連携による支援に診療報酬が加算、財源化され、ますますニーズが高まっています」
超高齢化社会に突入した日本では、要介護高齢者の介護課題や地域の在宅・生活復帰への支援取組みや医療費削減といった課題が生じています。要介護高齢者の患者様の中には、認知症が進む方も多く、転倒や徘徊などによるリスクも出てきます。そのため、介護者の見守りが負担となっております。病院から地域の在宅・生活復帰への多職種連携による支援に診療報酬が加算されるようになり、多職種連携自体が財源化され、ますます重要性が高まっております。しかし、診療報酬に加算されないコストのかかる部分、例えば月々のデータベース作成・管理料や見守りシステム等を製品化したものの利用料などの削減が課題となっております。
【谷口校長】
想像はしておりましたが、要介護者の見守りは大変な苦労がありますね。
【松井管理部次長】「奈良県にある福祉関連施設の職員・民生委員・福祉ボランティア団体などが一丸となって、要介護者の日常的実態や福祉ニーズを把握することが大事です」
在宅医療での要介護者の見守りは、ケアマネージャーの方が直接出向き安否確認するケースが多く、大きな負担になっております。「見守りの間隙を突き万が一事故があったら大変!」という危機感が常にケアマネージャーを襲います。現実には要介護者からの何らかのシグナルが発信されていなければ危険に気づくのが遅れるケースも考えられます。
その為に、地域が一丸となって要介護者を見守る必要があり、奈良県にある福祉関連施設の職員や民生委員・福祉ボランティア団体などが日常的に実態や福祉ニーズを把握することが大事です。しかしながら、介護の人材不足や多職種連携コミュニティの形成までには時間がかかります。そこで、奈良高専と協力して安全性を重視した要介護者見守りシステムの完成が急がれます。
【谷口校長】
現在、共同で検討中の要介護者見守りシステムも結構難題がありそうですね。
【松井管理部次長】「要介護者見守りシステムが介護の人材不足や業務負担を解決する1つの方法となります」
カメラなどを使って映像による監視となると、個人情報保護の観点から障壁があります。情報漏えい問題なども出てきますが、命にかかわることですので、個人に了解を得て安全性を重視し慎重に対応しております。現在、奈良高専と取り組んでいる要介護者見守りシステムでは、プログラムで個人の行動を正常行動と異常行動に自動判別するという難題に挑戦頂いております。
【瀬川院長】「病院情報システムには大きなコストがかかると同時に、専門のエンジニアも必要です」
病院内には豊富なデータの蓄積があります。電子カルテなど病院情報システムを構築して病院内のあらゆる部門がネットワークで連携し、業務の効率化・情報の共有化・患者サービスの向上などに役立っており、今後も医療のIT化の普及が小規模病院や診療所の電子化などで見込まれております。しかし、データベースやシステムの更新などメンテナンスには大きなコストがかかります。また、そういったシステムを構築できる専門のエンジニアも必要になります。
|
【早川教授】「長期インターンシップで技術系学生の受け入れを検討していただきたい」
病院内でのシステム構築の一助として、技術系学生のインターンシップ活用も考えられます。技術系学生の病院へのインターンシップはこれまであまり行われてき ませんでしたが、医療現場ではなくシステム構築という分野なら、学生にとっては新たな活躍の場の発見、病院にとっては技術者不足の解消という双方のメリッ トが生まれるかと思います。これまでのような短期のインターンシップ制度では学生の勉強としては時間が足りないので、1か月程度の長期インターンシップ制 度の検討が必要になってきます。また、インターンシップを通じて学生から斬新なシステムアイデアが出てくることも期待できます。これを機に病院でも技術系 学生のインターンシップ受け入れをご検討頂ければありがたいです。
|

|
|
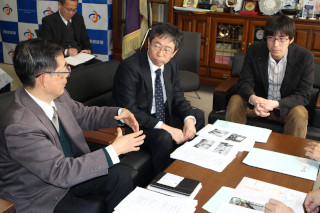
|
【松井管理部次長】「開発だけではなく既存のセンサーや技術素材などを活用してコストダウンをはかっていきたいです」
シ ステム構築には、工程の数、コストの両面でできるだけ負担を軽減し開発効率を高めるため、既存のセンサーや技術素材などを可能な限り活用していくことも一 策かと思います。今あるゲーム機の技術部分などをうまく活用してコストダウンをはかるといったやり方です。そのような可能性も視野に共同研究を進めていけ ればと考えております。
|
【谷口校長】
1本で約2km四方をカバーできるアンテナがあり、例えば学内に設置すれば、学生の行動もモニターできるといった話を聞いたことがあります。また、天井に貼り付けて8~10畳ほどのエリアをカバーする名刺サイズのセンサーもあるので、それらを使えば、電話回線やキャリア通信より利用コストも低くて済むかもしれません。
【松井管理部次長】「製品化には、地域性に合わせた機能とコストの両面からのアピールが求められます」
こんなものがあったら便利というだけでなく、これだけのわずかな利用料で使えるといった機能とコストの両面からアピールが求められます。それは地域によって様々ですので、その地域性にあったものを提供していくことが求められています。月1000円程度の負担でも難色を示される方はたくさんおられます。とかく初期費用に目が行きがちですが日々の運用・管理費用が利用者となる患者様やご家族の大きな判断基準になることが多いのです。

【谷口校長】
地域包括ケアに向けたシステムづくりには色々な課題があることを改めて認識しました。そういった課題解決に向け、若い技術系学生たちの発想・アイデアをうまく活用できれば、新たな展望が開けるかもしれません。先程のインターンシップの話も含め、貴病院と弊校との新たな連携の仕組みも模索していければと思います。
【松井管理部次長】「学生の若い発想やアイデアをインターンシップで活用できれば有意義です」
地域包括ケアでは栄養管理も重要です。地方創生事業(COC+)で奈良高専と協働されている奈良女子大学には栄養士の資格がとれる学部もあります。そのような学生さんのインターンシップにより若い発想やアイデアが活用できれば有意義です。
【谷口校長】
ご多忙な中、貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございます。
地域包括ケアの重要性と課題に関し色々なお話をお聞きすることができ、今後の済生会奈良病院様と本校との医工連携の新たな道筋のヒントにしていきたいと思います。
現在取り組み中の共同研究テーマを含め、今後も貴病院との連携を深め、地方創生に邁進してまいります。
※今後も済生会奈良病院様とは、医工連携分野の色々なテーマで連携を深めていくことを確認し合い、和やかに対談を終えました。