
本年度後期の専攻科2年の授業である『社会技術特論』では、地域創生演習科目として、学生たちが地域創生を通じた社会貢献の学びの重要性を理解し、また、奈良県吉野郡下市町の「林業」・「農業」・「商業」の各産業が抱える実際の問題をテーマとして、技術者の立場からの課題解決策の検討に取り組んでいます。
今回の授業の一環として、10月14日に下市町を訪問し、現地調査を実施致しました。本調査では、下市町役場、並びに各産業の現場を訪問し、関係者各位より生の声をヒアリングするとともに、学生たちは各産業の実際の作業を体験することで、現場から解決すべき問題を発見する試みがなされました。
午前中は、下市町町役場にて、町が抱える問題について、高齢化における後継者問題や、空き家や休眠農地の問題などについて、説明を頂きました。
午後からは、林業・農業・商業班に分かれ、各産業の作業現場を訪問し、関係者より、各現場が抱える問題について説明頂き、学生からは活発な質疑応答がなされました。
|
○林業
吉野銘木様に訪問し、吉野の杉や檜などに対する説明を受けました。特に、吉野の樹木は樹齢が長く、先祖代々手入れの行き届いた森林があるからこそ太く、大きな材木の提供が可能であるため寺社仏閣やお城の高級建築材とし利用されているとのことでした。また、伐採した樹木の加工現場や保管の仕方、そしてモデルハウスも見学させていただきました。様々な木材によって適性があり用途によって使い分けることで丈夫で長持ち、あるいは部屋の温かみも変わるなど説明いただきました。技術課題としては、樹木の乾燥を制御するためのシステムや伐採する樹木の内部構造を簡易に測定する技術が求められていることがわかりました。
続いて今も手作りで吉野杉を使った「らんちゅう」型の割り箸を作り続けている頃橋銘木店様を訪問させていただきました。手作りでの割り箸づくりにも挑戦させていただきました。現在、流通している割り箸の多くが竹材で、大量生産品であることを教えていただきました。吉野割り箸は高級料亭などでも使われているようで日本の食文化の発展とともに割り箸の技法も種々あるようです。
|

|
学外研修・下市町現地調査
 |
○農業
農業に関しては、菊井農園様を訪問し、柿栽培の現状について見学させて頂きました。午前中の町役場での説目で耳にはしていたものの、猪や鹿によって荒らされた畑の被害状況を実際に見てその深刻さを実感しました。この5年の間に猪の生息数がかなり増加しており、対策に苦慮している様子がわかりました。柿の収穫では、不安定な地面に脚立を立て、何度も上り下りしなくてはならず、トラックに積むまでの重労働となる様子を確認しました。
次に堆肥工場を見学させて頂きました。化学物質を使わない農業を推進しており、“おから”を原料として用いた堆肥を生産販売しており、評判は上々とのことであるが、製品になるまで2年かけて発酵させる必要があり、採算性の向上が課題であるという説明がありました。
最後に、菊井様が代表を務めるNPO法人による、農村における障害者支援活動内容の一端として、喫茶店における就労支援状況について説明頂きました。具体的ニーズとして、車いすによる接客の際の商品把持の安定化が課題となっているという説明がありました。
|
|
○商業
町役場のご担当者様の案内で、札の辻ステーションを訪問しました。ここでは、町の活性化を目指し、県外から募った人材によって10月下旬に下市町で初めてのパン屋がオープンされます。札の辻ステーションは、観光客が車で行きかう幹線道路沿いにあり、この新しい商業施設への集客が期待されることの説明がなされました。
また、松村酒造様に立ち寄り、現在は、ネットでの販売が中心ではあるが、町の活性化にはやはり町に人を運び込むことが重要であるとのお話を頂きました。
その後、創業明治15年の吉野葛の製造・販売されている吉田屋様が運営される「おばあちゃんのミニ博物館」を訪問し、葛菓子の手作りの製造方法をご説明頂きました。また、学生たちは実際に葛菓子作りを体験しました。
|
 |
今回の現地での調査、体験を学校に持ち帰り、技術者の観点から下市町が抱える問題を抽出し、課題発見・課題解決につなげていくとともに、これらのワークを通じ、学生たちが社会との関わりの中で、課題設定能力・課題解決提案能力を身につけ、実践できるように講義を進めて参ります。
お忙しい中、ご協力いただきました下市町役場様、菊井農園様、吉野銘木様、頃橋銘木様、吉田屋様、松村酒造様に感謝いたします。
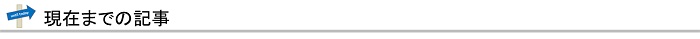
社会技術特論