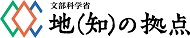
平成29年2月10日(金)、『奈良高専OB・OGが勤める県内企業様&奈良高専 交流会』を開催し、本校卒業生を含む12社22名の県内企業様にご参加いただきました。
この交流会は、本校OB・OGが勤める県内企業様と本校教員との情報・意見交換を通じて、卒業生の活躍状況や企業の求める人材像、求人・雇用における課題や本校教育に対する期待などをお聞きし、さらなる信頼関係を深めていくことで地域における雇用創出、学生の地元定着の向上を目指して行われました。
はじめに、総合司会者である牧野学生課長より、本校出席教員13名の紹介があり、後藤校長より開会のあいさつが行われました。
つぎに、COC+実施本部 副本部長 藤田教授より、「COC+事業紹介」があり、さらに、学生主事 片倉教授より、「本校学生の進路状況等について」の報告がありました。
その後に、参加企業様より自己紹介をしていただき、本校からは本科5学科代表の教員から「各学科の近年の進路状況と学生動向の紹介」がありました。
参加企業様に2つのブロックに分かれていただき、卒業生の活躍状況や本校教育に対する期待等を各企業様よりご意見をいただきました。
|
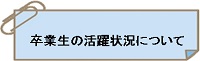
ご参加いただいた12社の出席者のうち5社の企業様に奈良高専卒業生がおられ、その他の企業様におかれましても多数の本校卒業生がご活躍されておられました。主に、機械やアプリケーションに係わる開発・設計、研究・品質検査や営業などの多岐にわたる職種に携わっておられ、若手リーダーや幹部として活躍されております。
入社当初は、工場で現場を経験し、現場の仕事を知ったうえで配属が決まる場合や研究開発からさらに、企画開発にも参加する場合(ジェネラリスト)等、個人の適性に応じてキャリア形成ができる企業様のお話も伺えました。
活発な意見交換の中、本校卒業生である企業様から後輩である奈良高専学生へのメッセージもいただきました。
「メーカーにとらわれず、自分の希望や能力を活かせる企業への就職を希望してください。」
「弊社には、自分の設計した機械が商品化する喜びがあります。"ものづくりがしたい"、"高専での研究等の取組みを活かしたい"そんな方に向いています。」
「職場で自分の意見を述べるときに、高専で学んだ知識が役に立ちます。ロボコンや卒論発表等で積極的に発言して、相手に伝えることを学んでください。」
「高専卒業後は、県外で大手企業に就職しましたが、家庭の事情により奈良県にUターンして再就職することとなりました。その際に、学生当時の担任教員から現職をご紹介いただきました。高専生の3つの強み、"知力・体力・精神力"を活かして色々な対応力で、活躍ができる場が(奈良県には)あります。」
|
|
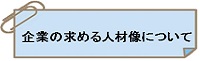
ご参加いただいた多くの企業様が、高専生の基礎能力・専門知識の高さや実験等を通して学んだ ことを現場で即戦力として活かせる人材として期待しておられます。さらに、卒論発表等でのプレゼンテーション経験からコミュニケーション力の高さにも注目されている企業様がございました。
職場はチームで働く場所であり、多様な人々と仕事をしていく必要があります。そのために、職場の雰囲気をよみ、色々なことに対応できる柔軟性のある人や2交代・3交代の仕事にも対応できるバイタリティ溢れる人やクレームにも対応できる機転がきく人、探究心の あるタフな人、「ものづくり」がしたい人などが企業の求める求人像として挙げられました。
|
|
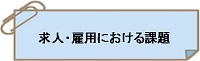
企業には、一人一人がそれぞれを認めて、色々な人を受け入れたうえで仕事をしていくことが必要です。職場の雰囲気をよみ、助け合いのできる体制づくりを心がけている企業様もございました。また、女性が育児と仕事の両立ができるように、産休・育休が利用しやすく職場復帰しやすい制度づくりを目指している企業様もありました。
工場での2交代・3交代の仕事では、有給休暇の取得率が、なかなか上がらないのが実情であり、その対策として、「従業員数を増やすことで対応する必要がある。」と述べられた企業様もございました。給与面では、大企業並みにはいかないのが現状であるが、大学卒と高専卒とでは「初任給こそ差がありますが、その後は個人の頑張り次第で給与面で大差ない場合があります。」と 述べられる企業様もありました。
また、これまでは、奈良高専で新卒者だけの募集をしていたが、「第二新卒や既卒者等の募集や奈良県へのUターン希望者の採用受入にも積極的に取り組みます。」との企業様のお声も頂きました。
|
|
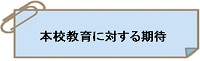
「学生に、会社の良さを知っていただくためにインターンシップや工場見学の受け入れを行っています。事業内容に興味があれば、積極的に参加していただきたいです。」
「専門知識をしっかり磨いて頂き、加えてコミュニケーション力を養ってもらいたいです。また、業務として、簡単な英語で伝える機会があるので、学生のうちに語学力を伸ばす教育が必要です。」
「奈良高専に求める教育として、基礎をしっかりと学んでいただきたいです。できれば、基礎を発展させる実践のために、一歩踏み出す仕方を学生に教えて頂けると助かります。」
「奈良県へのUターン希望者が多い現状を踏まえ、そのニーズに応えるための高専卒業生の追跡調査をして、地元就職に活かしてほしいです。」等、多くのご意見をいただきました。
|
これらに対して、本校教員からも活発な意見が出されました。
学生に奈良県企業の魅力を知ってもらう、きっかけづくりが非常に大事です。そのために、技術相談や共同研究等で企業様に研究室や実験室に足を運んでいただき、学生との直接交流を通して、企業が学生を知る場をつくることや企業のインターンシップ・工場見学の受け入れを通して、学生に現場を体験してもらい、企業をアピールしていただくことで、学生が企業を知る場をつくることがこれまで以上に必要となっています。学生だけでなく、教員や保護者も企業を知る必要があります。そのために、企業の魅力を伝えるインセンティブのような要素や入社後に高専生の能力を引き出せる制度等があればよいと思います。企業様にも本校と共に、お力添えいただければと思います。
最後に、地域創生研究センター長である早川教授より、閉会のあいさつが行われました。
閉会後には、名刺交換を含む自由歓談の場が設けられ、会場内に、かつての学生と恩師の姿も垣間見られ、うちとけた一時となりました。
本校の地方創生の取組として、産学間で初めて開催されたこの交流会を通して、奈良県にUターンして再就職した本校卒業生が少なからずおられること、またそのような人材を求める企業様が多数あることを知り、地域における雇用創出へのさらなる課題を発見する有意義な場となり、また、本校と参加企業様の信頼関係を深めていく好機となりました。