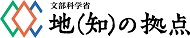
平成28年1月15日(金)
専攻科2年生の授業科目「社会技術特論」において、奈良女子大学大学院人間文化研究科の寺岡伸悟教授をお招きして、特別授業を行いました。「社会技術特論」は、専門学科教員による最先端技術についての講義、弁理士による特許についての講義等を15回にわたってオムニバス形式で進めて行く授業で、技術者・研究者として社会に貢献するために必要な幅広い視野を養成することを目標としています。今回は、COC+が開始されたことも踏まえ、事業協働機関である奈良女子大の寺岡先生に、「技術者にとっての地域創生」というテーマで講義をいただきました。本校でもいよいよ、地域創生関連授業がスタートしました。

(授業風景1)
寺岡先生より、取り組んでこられたモデル事業(高齢者の営農を支える「らくらく農法」の開発 )を事例に過疎対策の難しさを学生に紹介いただきました。技術と社会の関係において、技術の進歩と社会の変化がマッチしたときにはじめて技術は普及するとの言葉に学生は感銘を受けたようでした。

(授業風景2)
寺岡先生が過疎対策の研究に取り組まれたときに、吉野の柿農家との出会いがありました。奈良県の名産である良質な柿を生産する背後には農家の方々の重労働がありました。大量の柿の入ったかごを働き手(特に高齢者)がとても苦労して運搬しなければならず、重量物の運搬労働の軽減が求められていました。
寺岡先生は、奈良県や地元企業、奈良高専を含む多くの大学と研究グループを作り、JSTの戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)に申請し、採択されました。このプロジェクトの目的は「高齢営農者があと10年長く営農を続けられ状況をつくることで、農村コミュニティの衰退、荒廃を抑制すること」でした。つまり、農村コミュニティを高齢者の生きがいの豊作地帯(らくらく・楽しく・仕事有り)にすることを目指し、①コミュニティ、②生業(農業)、③道具(機械)、④からだ(健康)の4つの側面からの支援を実施されました。具体的には、高齢者の方が扱いやすい「新しい電動運搬車」、「らくらく栽培」システムを導入、営農者の身体点検と怪我の予防体操「らくらく体操」なとに取り組まれました。

(授業風景3)
このプロジェクトでは、研究グループと地元住民が連携して作り上げ、そこで異文化交流、一緒にものづくりに取り組めたことに大きな価値があるとのことでした。
奈良県には、特に南部東部地域には典型的な地方の少子高齢化問題があること、いわゆるベッドタウンが高齢化し空洞化する状況の中、いかに街を再活用できるか、県外消費全国1位等の取り組み課題があり、COC+事業を通じてこれらの課題に取り組み、地域創生の一端を担いたいとのことでした。

COC+ 政治・経済(2016年10月6日掲載)
『地域の課題を解決するアイデアを出そう』~本校教員による地域創生授業が実施されました~(2016年2月3日掲載)