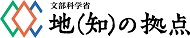
専攻科2年生の『社会技術特論』(全専攻必修科目)で,年初に奈良女子大学の寺岡先生をお招きして地域創生の講義をしていただきましたが,今回は,本校機械工学科の福岡寛講師よる地域創生のワークショップを実施しました。(平成28年1月29日(金)) 先生の専門である流体力学と参加学生自身の専門知識を組み合わせて,地域の課題解決のためのアイデアを出そうという演習です。90分の講義の前半15分で簡単な流体力学の説明があり,その後,さっそくワークショップに入りました。専攻科2年の学生は,1年生の時に『システムデザイン演習』で問題解決のための話し合い技術(ファシリテーション技法)を学んでいますので,開始後,すぐに話し合いが進んでいきました。
特に,今回は農業分野での課題についてアイデアを出し合いました。1班は,土砂崩れの問題について考えました。土砂崩れの予想をするセンサーなどのアイデアが出ました。2班は,都会でできる農業「スマ農」-IT技術などを使って農業のイメージを変える提案がなされました。3班からは,「女性が働きやすい農業」にフォーカスされたアイデアが出されました。「虫対策」「手が汚れる」「腰をかがめる必要がある」など女性が農業を敬遠することに対する対応策が提案されました。4班は,農業の課題を総合的に解決する方法として「モニタリング技術」を中核に据えたアイデアが出されました。そして,最後の5班のアイデアは,「自然と植物の関係を明らかにすること」が重要であると考え,植物の育成状況を測定し,それをデータベース化というものでした。限られた時間の中で,参加学生も満足できる話し合いがなされました。技術者として地域に貢献できることは何かと考えるきっかけになったと思います。

話し合いの流れを書いたアジェンダ(会議進行表)

付箋を使って,アイデア抽出。 アイデアの評価も100ドル法というユニークな方法

班ごとの 発表風景です。

COC+ 政治・経済(2016年10月6日掲載)
地域創生授業が始まりました(2016年1月25日掲載)