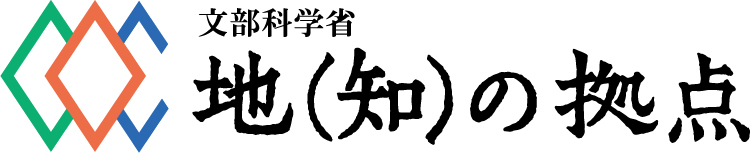
<テクノス株式会社様との対談>
2月23日(火) 本校 谷口校長と地方創生研究センター長 早川教授がテクノス株式会社を訪問し、代表取締役社長 八重津 真彬様、チーフエンジニア 神戸 和子様、マネージャー 吉村 謙二様との対談が行われました。
テクノス株式会社様とは「歩行訓練用高機能靴」や「介護ロボット」などの開発において本校と密接な協力関係にあり、計測・制御・回路技術を中心に優れた技術開発力を保有されている県下の有力企業です。
社長の八重津様は、電機メーカーご出身で、それまでのご経験を活かし自ら起業されたチャレンジ精神旺盛な経営者であられます。この度の対談で、これまでの多くの貴重なご経験をお聞きし、地方創生事業(COC+)に取り組む本校へ多くのヒント・応援メッセージを頂きました。

(早川教授・谷口校長・八重津代表取締役社長・吉村マネージャー)
【谷口校長】
ご多忙な中、貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございます。
テクノス株式会社様とはこれまで色々な研究開発テーマでご協力頂いており、また、本校学生の有力な就職先として、卒業生を採用頂くなど、大変お世話になっております。
お付き合いの深い御社の目から見た本校の印象や本校に対するご要望・期待など率直なご意見を賜ればありがたいです。
|

(八重津代表取締役社長)
|
【八重津社長】
「自分の人生をじっくり見直してみることが大切です」
起業前に勤めていた大手電機メーカーには、45歳を契機に自分の人生を見直そうと漠然とですが、心に決めて入社しました。人生の半ばで自分の身の振り方をじっくり考えることは後半の人生をより有意義にするために大切なことだと思います。
自 分も会社内で地位が上がるほど開発現場から遠ざかり、やりたいことができないというジレンマにかられました。「自分は一生技術職で行こう。」という思いが 募ったのが、管理業務が増え、技術的仕事が出来なくなる45歳頃だったこともあり、思い切って退職し起業を決心しました。 |
|
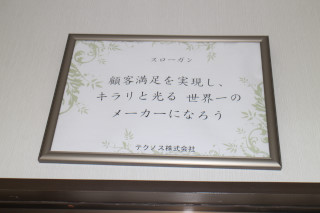
(テクノス株式会社様スローガン)
|
【谷口校長】
一言に起業といっても大変なご苦労があったかと思います。
|
|

(スマートリペア装置)
|
【八重津社長】
「外を見る。誰とでも会える。顔見知りづくりにより、たくさんの人たちに助けられて今日があります」
起業時は社員3名でスタートしましたが、仕事探しには困りませんでした。電機メーカー時代にたくさんの企業と知り合いになり、その幅広い人脈が起業後のビジネスで大きな支えとなりました。
|

【谷口校長】
新たな会社では若い人たちの雇用確保が課題だと思います。
【八重津社長】 「若手確保には大学とのつながりが大切です」
これまで大学との共同研究も積極的に行ってきました。例えば、平成13年に熊本大学構内に「熊本研究所」を設立し、新しい概念の露光装置の共同開発プロジェクト(熊本大学、ソニー、熊本テクノロジー)をスタートさせました。経済産業省 新事業創出促進法による新事業分野(FPD品位検査装置)開発実施計画の認定を受けました。
学生たちにはプロジェクトに取り組んでもらい、その成果が博士論文に結びつけば、企業・学生(大学)双方のメリットが生まれます。
そうすることで学生の間で企業の認知も広がりイメージアップにも繋がります。当時から大学に民間企業を呼び込む産学関係がありました。
【谷口校長】
事業として色々と多岐に渡り手がけておられますね。
【八重津社長】 「低迷も経験。厳しいハードルを乗り越える時代を社員が耐えてくれたから、今があります」
一時、液晶関係の仕事に特化していた時期もありましたが、周知のごとく液晶事業がコスト競争激化で厳しい状況になりました。会社の低迷を経験したこともありましたが、社員がよく耐えてくれました。それ以降、分野を問わず、色々な仕事に手を広げるようになりました。社員の苦労も多かったと思いますが、この社員の頑張りが今の会社を支えております。ものづくりには、業種を問わず必要な業務に『検査』があります。品質検査、動作検査、耐久検査など今ではかなりの部分が自動化されておりますが、それでもどのメーカーも必ず目視検査の工程は残っております。例えば、タイルの色合検査・外寸検査。繊維のほつれ・しみ。香料カプセルの検査。米の異物除去検査など。メーカーにとって目視検査が課題であり、そこに色々なビジネスチャンスの芽があります。高度な注文が多く社員は苦労しておりますが、その分、やりがいも大きいです。
 |
 |
|
【谷口校長】
奈良高専への要望・期待をお聞かせ頂きたいです。
【八重津社長】
「高専の学生は実践に強く、力があります。全国的に価値をアピールしましょう」
高専の学生は、はんだを持つ回数が違います。ものをよく触っているので、実際に物事を実験し評価するという経験が豊富です。学士の学生とは教育の仕組みが違うので、ものに触れる機会の多い高専学生は、企業から見れば非常に実戦向きで即戦力として高く評価しております。全国的に高専の良さをもっとアピールしていくことが大切です。
|
【八重津社長】
「何がやりたくて就職するのか、自分のビジョンを持とう」
日本の企業の欠点は、人材を枠にはめるところです。「高専の学生なら、この範囲の仕事をしてもらおう。」のように、枠にはめてしまったら、本来企業は人材育成の面で損をします。また、一定の年齢になると開発や設計といった技術職からマネージメントばかりの管理職へ出世し、技術的仕事が出来なくなる年齢が来ます。これでは、折角の技術者を潰していると思います。この点からも、単に規模や知名度だけで企業を選ぶ時代は終わったように感じます。技術者にとっては、企画、準備、作製、検査といったものづくりの流れを直接携わることでやりがいへとつながります。本当は何がしたいのか。何になりたいのかを考え、学生本人が真の力をつけていれば、どの企業でも通用致します。
|
|
【早川教授】
現在、奈良高専では、地方創生事業(COC+)活動の一環として色々な機会を通じて学生たちが企業のものづくりに触れることでその企業の良さを体感する取り組みを進めております。地元の中小企業にも特色ある魅力的な企業がたくさんあります。それら企業では学生たちのやりたい仕事ができる機会もたくさんあり、地元への就職、地方創生の一助となればと考えております。
|
【谷口校長】
自分たちの思い入れのある仕事が商品化に結びつき世の中から評価を得るといった、この「見える化」が大切かと思います。奈良高専では、技術者育成のためにレクチャーだけではなく、実例を通した教育に取組んでいます。その為にも、この度の地方創生事業(COC+)で地元企業との結びつきを深め、企業と学生双方がその良さを認め合う機会をたくさん作っていきたいと思います。
|
【八重津社長】 「企業体験は実のあるものに」
企業や高専側の事情が許せば、インターンシップの期間をもう少し長く設定して頂きたいと思うのですが。そうすれば、その期間学生に必ず何かを掴んでもらえるようにできると思います。現在のインターンシップは短期間(1~2週間程度)の為、職場の雰囲気に慣れた程度で終わってしまうケースが多いので、もったいないです。
【吉村マネージャー】 「自分で仕事を広げていける楽しみは中小企業にあります」
インターンシップの期間が、せめて1か月程度あれば習得できるスキルも増え、実作業寄りの仕事を任せることができるようになります。共同研究などでも、一緒につくって問題がわかれば、学生のスキルアップにつながります。
大手企業の技術者の皆さんが当社を訪問されると、「実はこういう仕事がやりたかった」と羨ましがられることがよくあります。やりたい仕事は実は中小企業に多くあり、自分で仕事を広げていく楽しみは大手企業より味わえるのではないかと思います。
【早川教授】
インターンシップの期間調整は可能ですので、今後長期化については検討して参ります。
インターンシップ等の企業体験を通じて学生が考え、斬新なアイデアを企業で活かし
てもらうことができれば、学生、企業の双方でメリットが生まれます。
【神戸チーフ】 「技術者にも英語力が大切」
世の中の論文の大半が英語です。最先端の技術情報入手には英語力が不可欠な時代であり、技術者への英語教育に力を注いでいかなければなりません。
【早川教授】
語学は慣れです。実際、昔は奈良高専の学生の英語力評価は低かったです。しかし、今は海外交流や専攻科推薦入学要件にTOEIC最低基準点を設けております。国立高等専門学校機構においても英語力向上に関する取組が行われております。その成果もあり、奈良先端科学技術大学院大学から奈良高専の学生の英語力の向上を高く評価していただく声を聴いております。
【谷口校長】
これまでのご経験から様々な教訓・アドバイスを頂き、今後の高専の歩むべき道のりを示して頂きありがとうございました。
ものづくりを通じた地元貢献を実践して行くために頂いた多くのヒントをもとに、今後も高専教育の改革に邁進してまいります。本日は本当にありがとうございました。

※今後もテクノス株式会社様とは、色々なテーマで本校との連携を深めていくことを確認し合い、和やかに対談を終えました。