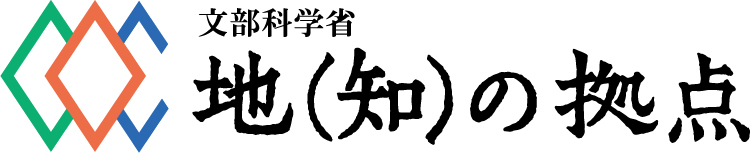
<三晃精機様との対談>
2月4日(木)、三晃精機株式会社 代表取締役社長 笹岡元信様が来校され、本校 谷口校長、地域創生研究センター長 早川先生との対談が行われました。
三晃精機様とはこれまでも共同研究等で当校と協力関係にあり、現在も農工連携分野で共同研究に取り組んでおります。
社長の笹岡様は経営者であられると共に、これまで業界・業種を問わず全国の様々な企業、事業者、個人から寄せられる切実なニーズに応えアイデア商品を数多く生み出してこられた「ものづくり魂」に富んだアイデアマンでもあります。
この度の対談で、これまでの多くの貴重なご経験をお聞きし、地方創生推進事業(COC+)に取り組む本校へたくさんのヒント・応援メッセージを頂き、有意義な対談となりました。

( 谷口校長 ・ 笹岡代表取締役社長 ・ 地域創生研究センター長早川先生 )
【谷口校長】
ご多忙の折お立ち寄り頂き有難うございます。
【笹岡様】
奈良高専とは長い付き合いです。きっかけは電気工学科の故 高橋晴雄教授でした。高橋教授を訪問の折、偶然同級生だった電子制御工学科 阪部俊也教授に出会いました。ちょうど光の研究を始めたタイミングもあり、光を専門としている阪部教授と(光をテーマとする)アグリビジネス研究に取り組むことになりました。採択6件の中に入り、5番目だったのですが、事業終了時には1番の評価を頂きました。結果、稲の結実成長を阻害する光をカットした照明灯を開発しました。奈良高専、奈良先端科学技術大学院大学との共同研究で成果は奈良先端科学技術大学院大学から”サイエンス”等世界に発表しました。
また、柿の葉を紅葉させる方法について奈良県農業研究開発センターと奈良高専阪部教授、また奈良女子大学の寺岡伸悟教授と共同で研究に取り組みました。
柿農家は高齢化しており柿の実は非常に重く重労働です。そこで柿の葉に着目しました。
実が美しく紅葉した柿の葉は高級料亭に使用され、良質な葉ですと柿の実10個分の値段で売れます。これなら重い柿の実とは違い高齢者の仕事としても十分に行えます。
カメムシも研究しました。光の質によってカメムシの行動を制御できるのです。黄色灯577ナノメートルの波長の光をカメムシに当てると行動が抑制され交尾まで制御できることがわかりました。これは昆虫学会で非常に評価されました。
その後、奈良県警から痴漢防止のためにどういう街灯の光が良いか研究して欲しいという依頼があり、青色光の照明灯を開発し実証実験にも参画しました。
【谷口校長】
既に立派な地域創生の取り組みをされておられますね。
【笹岡様】

■「何とかしてあげたい」という熱い気持ちこそ「ものづくり」の原点!
商品のヒントは色々な人々の苦労から得られます。そんな切実な願いをただ聞くだけでは折角のアイデアの種も隠れてしまいます。
そのアイデアの種を育てる最大の肥やしは「何とかしてあげたい」という熱い気持ちであり、それこそがものづくりの原点です。
■まずは作ってみる!そこから信頼関係が生まれる!
人々の切実な願いは形にしてあげてこそ感動を与えます。まずは作ってみることです。これまで色々なものを作ってはビジネスにならなかったことも多々あります。しかし、多くの失敗の積み重ねが次のアイデアのヒントになり、ヒントをくれた人との信頼関係も生まれます。「言ったことはやってくれる」これこそが信頼です。その中からいくつかでもビジネスとして成長できれば会社も大きくなっていきます。
■失敗はアイデアの宝庫!必ず次につながると信じよう!
これまでの様々なアイデア商品のほとんどがビジネスにならなかったが、それに屈することなく、粘り強くトライしていくことが次の成功につながります。そこには人との信頼関係という財産も積み重なり、実になっていく。そういう信念で仕事をすることが大切です。
■現場のニーズはその土地に足を運んで困っている人と一緒に体験する!
何に困っているかは実際に体験しないとわかりません。ものづくりは、自身がユーザーとなり課題を体感することで真のアイデアが生まれます。
■社会への貢献がビジネスの生命線!
JSTの戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)に申請し採択された『高齢者の営農を支える「らくらく農法」』プロジェクトを目的として、また、ビジネスとしても開花した商品に「電動一輪車」があります。高齢の方が重い農作物を苦労して人力で運んでいる光景からヒントを得て、「高齢者でも重い荷物を楽に運べる道具がつくれないか」という一念から生まれた商品です。
この「電動一輪車」を全国に紹介して回るとたちまち大きな反響があり、農作業等荷物運搬の重労働から人々を解放する一助となりました。社会への貢献ができてこそビジネスは広がります。
|
■高齢化対策は日本だけの問題ではないもっとグローバルな視点で取り組もう!
高齢者への対策は日本だけにとどまらず全世界的な課題です。そこでこの「電動一輪車」を世界にも広げ、より多くの高齢者に届けようと、2014年にトルコでの学会に出席し「電動一輪車」を披露しました。
多くの出席者から絶賛を浴び、実際に現地の農場で農夫の方にも使って頂いてその便利さを体感してもらい大好評でした。
これはトルコでの一例ですが、世界を見渡すとまだまだ多くの人がこの「電動一輪車」を待っています。
アイデア商品という宝物は日本だけにとどめておかず、もっとグローバルに貢献していくことが大切です。それによりビジネスも広がります。地域創生で国際交流がなしえたわけです。
|
 |
|
■常に開発型企業でありたい!
ものづくりは、日々新しいことへの挑戦です。1度の成功で慢心していたら次はありません。
2度目の成功があってこそはじめて本物と言えるのです。
日々邁進を続け、「電動一輪車」の姉妹品として「電動運搬車」も作りました。
|
 |

■クレームにくるお客様は真のファン!
クレームは期待の裏返しです。期待が大きいからこそ、それが裏切られたときの怒りは大きいのです。
どんなクレームも真摯に受け止め、丁寧に対応していくことで、その時は怒っておられたお客様も絶大なファンになっていただけます。クレームはアイデアの宝庫であり、そこから新たなヒントを見つけ新商品につなげていくことが企業の成長に結びつきます。
【谷口校長】
これまでのご経験から様々な教訓・ご意見を頂き、「ものづくりを通じた地域貢献」の極意を示して頂きました。本校がCOC+事業に取り組んでいく上で、その指針となるキーワードを幾つも頂き、大変参考になりました。笹岡様は全国で名の知られた有名社長であられ、そのような方の企業と一緒にアライアンスを組ませて頂くことは本校にとっても大変有意義なことです。
※今後も三晃精機様とは、色々なテーマで本校との連携を深めていくことを確認し合い、和やかに対談を終えました。