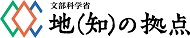
≪なら学+(奈良女子大学との単位互換科目)≫
奈良女子大学 地域志向科目「なら学+(プラス)~奈良を通じて地方創生への知見を深めよう!~」が後期開講されております。
本講義は、本校と奈良女子大学・奈良県立大学が連携した地方創生推進事業(COC+)の一環として、3校が取り交わした単位互換科目の一つとして実現し、毎週多彩なゲスト講師を招へいし、奈良の取組みや課題を異なる専門分野からの視点で学びます。平成30年10月2日(火)より全15回に渡って講義が進められており、本校から2名の教員が2回にわたり、奈良女子大学で講義を行います。
"COC+、地域づくり、地域リーダー、伝統産業、ものづくり、女性の働き方(ワーク&ライフバランス)、起業、社会福祉"等をキーワードに、毎週火曜日13時より奈良女子大学S235教室で行っております。
昨年度は、奈良女子大学の学生1・2回生を中心に174名の受講登録がありました。奈良高専の学生で興味のある方は、奈良女子大学の「なら学+(プラス)」を履修し、単位を取得することが認められております。
〈今年度の受講登録期間は終了しております。)
≪奈良女子大学 後期 講義内容(予定)≫
| 回数 |
日程 |
講義内容 |
| 第 1回 |
10 / 2(火)
13時00分~14時30分 |
成瀬 九美 やまと共創郷育センター長 前川 光正 COC+コーディネータ―
ガイダンス |
| 第 2回 |
10 / 9(火)
13時00分~14時30分 |
奈良県立大学 増本 貴士 特任准教授
"なら"でのコンテンツツーリズム~観光のニーズとその課題~ |
| 第 3回 |
10 /16(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良市観光協会 ②飛鳥観光協会
観光産業への理解を深め、課題を探る |
| 第 4回 |
10 / 23(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良県女性活躍推進課 ②株式会社Table a Cloth
女性の起業やワーク&ライフプランを考える |
| 第 5回 |
10 /30(火)
13時00分~14時30分 |
奈良佐保短期大学 武田 千幸 准教授
生活福祉を考える |
| 第 6回 |
11 /13(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良県社会福祉協議会 ②福祉現場の方
社会福祉法人・NPO法人の役割と課題 |
| 第 7回 |
11 /20(火)
13時00分~14時30分 |
奈良工業高等専門学校 藤田 直幸 教授
モノづくりを通じての地方創生 |
| 第 8回 |
11 /27(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良県森林技術センター ②株式会社イムラ
伝統産業(林業)への理解を深め、課題を探る |
| 第 9回 |
12 / 4(火)
13時00分~14時30分 |
奈良県靴下工業組合(株式会社キタイ)
伝統産業(靴下)への理解を深め、課題を探る |
| 第10回 |
12 /11(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良県薬事研究センター ②田村薬品工業株式会社
伝統産業(製薬)への理解を深め、課題を探る |
| 第11回 |
12 /18(火)
13時00分~14時30分 |
奈良工業高等専門学校 竹原 信也 准教授
地域社会における技術者の役割 |
| 第12回 |
12 /25(火)
13時00分~14時30分 |
①株式会社ATOUN ②DMG森精機株式会社
奈良の現代産業に聞く |
| 第13回 |
1 / 8(火)
13時00分~14時30分 |
①奈良県農林部 ②株式会社マックス
柿(奈良特産)のマーケティングを考える |
| 第14回 |
1 /22(火)
13時00分~14時30分 |
①下市町地域づくり推進課 ②奈良県地域振興部
地方自治体の役割・課題を探る |
| 第15回 |
1 /29(火)
13時00分~14時30分 |
南都経済研究所
なら学+(プラス)振り返りと活動発表・総括講演 |

平成30年度 COC+ 政治・経済
平成30年度 前期 地域社会技術特論
≪なら学+ 電気工学科 藤田 直幸教授 「モノづくりを通じての地方創生」≫

第7回 奈良工業高等専門学校 電気工学科 藤田 直幸教授 「モノづくりを通じての地方創生」
『なら学+』とは、奈良女子大学の後期(平成30年10月2日から平成31年1月29日まで実施)、全15回に渡って行われるオムニバス形式の講義です。各回には、高専や大学、企業や地方公共団体、公益法人等の教員や社員、職員が講師として招へいされ、様々な視点から奈良の魅力についてアプローチしていきます。本校と奈良女子大学及び奈良県立大学の学生が、相互に大学や高専の講義科目を履修し、単位を取得することを認めるもので、昨年度に引き続き今年度も本校から2名の教員が2回にわたり講義を行います。
平成30年11月20日(火)、奈良女子大学 文学系S棟 235教室にて、本校 電気工学科 藤田 直幸教授による『なら学+』の講義が行われました。
はじめに、奈良女子大学 前川COC+コーディネーターからガイダンスが行われ、「県内自治体の魅力を聞くセミナー」や「県内企業見学会参加募集」等の紹介、前回講義の意見や感想が伝えられました。
つぎに、藤田教授の紹介と共に、「モノづくりを通じての地方創生」と題して本日の講義が開始されました。
|

(奈良女子大学 前川COC+コーディネーター)
|

(本校 電気工学科 藤田教授)
|
| 本日の講演内容 |
①イントロダクション~奈良高専とはどんな学校か?~
②技術者と科学者
③奈良高専の地域創生に対する取組
④モノづくりにおける文系と理系のコラボレーション |
|
| 本日の講義の到達目標 |
以下のことについて説明することができる。
①技術者の仕事の本質
②モノづくりを通じて地方創生に貢献するための具体的な取組
③モノづくりにおける文系と理系のコラボレーションの効果 |
|
藤田教授は、イントロダクションとして"教育システム"や"カリキュラムの特徴"等から、奈良高専の紹介を行いました。
そして、「『技術と科学の違いとは、何か?』について、考えてみてください。」と投げかけ、学生は個人ワークを通してプリントへ各自の考えを記入し、発表しました。そして、工学という学問には、"幸せの追求"という方向性が内在されていることを説明し、「技術者の仕事の本質」についてまとめました。
(学生が各自の考えを発表する様子)
その後、本校の地域創生に対する取組について、これまでの地域貢献から地域創生へとギアチェンジする奈良高専の挑戦を"教育"・"研究"・"人材定着"の3つから紹介しました。そして、学生は「モノづくりを通じて地方創生に貢献するための具体的な取組」についてまとめました。
| 奈良高専の地域創生に対する取組紹介 |
|

(教育について)
|

(研究について)
|

(人材定着について)
|
さらに、藤田教授は「新製品を開発する場合、どのような流れで開発が行われると思いますか?」と投げかけ、学生は個人ワークを通してプリントへ各自の考えを記入し、発表しました。そして、「モノづくりにおける文系と理系のコラボレーションの効果」についてまとめました。
最後に、学生は本日の講義の到達目標について、自己評価を行い、アンケートを提出しました。
|

(講義の様子)
|

(アンケート提出の様子)
|
本校教員による次回の『なら学+』は、一般教科 竹原准教授による「地域社会における技術者の役割」と題して、平成30年12月18日(火)に行われる予定です。
≪なら学+ 一般教科 竹原 信也准教授 「地域社会における技術者の役割を考える」≫

第11回 奈良工業高等専門学校 一般教科 竹原 信也准教授 「地域社会における技術者の役割を考える」
奈良女子大学後期の講義(平成30年10月2日から平成31年1月29日まで実施)『なら学+』が、奈良女子大学 文学系S棟 235教室にて実施され、昨年度に引き続き本校から2名の教員が2回にわたり講義を行いました。平成30年度に奈良高専の教員が行う『なら学+』第一回目が平成30年11月20日、電気工学科 藤田 直幸教授にて行われ、この度で第二回目の講義となります。平成30年12月20日(火)、本校 一般教科 竹原 信也准教授による『なら学+』の講義が行われました。
はじめに、奈良女子大学 前川COC+コーディネーターからガイダンスが行われ、「3校合同 県内企業見学会」等の紹介、前回講義の意見や感想が伝えられました。また、この講義の最終レポートについて、前川COC+コーディネーターが作成したレポートが、『奈良への提案』と題して、観光編と林業編の2つのプラン例が紹介されました。
つぎに、本校 一般教科 竹原准教授による「地域社会における技術者の役割を考える」と題して本日の講義が開始されました。
|

(奈良女子大学 前川COC+コーディネーター)
|

(本校 一般教科 竹原准教授)
|
| 本日の講演内容 |
|
はじめに:自己・学校紹介等
①地域社会の重要性
②奈良地域
③科学者と技術者
④科学技術と社会
⑤地域社会における技術者の役割
おわりに:提出シート記入
|
|
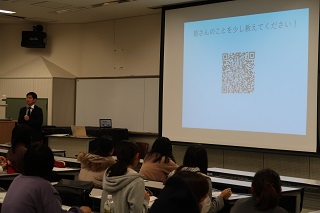 |
竹原准教授から自己紹介を兼ね学生に「皆さんのことを少し教えてください。」と、QRコードを活用して質問が出されました。
|

(学生がスマートフォンでQRコードを読み取る様子)
|

(入力したアンケート結果が表示される様子)
|
そして、「地域社会が今、なぜ重要とされるのか」と投げかけ、地域社会学とグローバリゼーションの視点から説明し、学生はプリントへ各自の考えを記入し、奈良県の今と・これからについてまとめました。
その後、学生は「技術者(エンジニア)と科学者(サイエンティスト)」のイメージや違いについて考え、まとめました。
|

(学生が各自の考えを発表する様子)
|
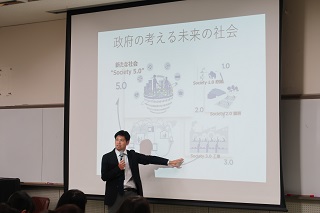
(講義の様子)
|
さらに、竹原准教授から「科学技術と地域社会」について説明がなされ、「あなたの描く未来の社会とは、どんな社会ですか?」と投げかけ、学生は「未来の良いところ」「未来への不安」についてプリントへ各自の考えを記入し「地域社会における技術者の役割を考える」ことで、本講義の内容をまとめました。
途中で、アイスブレークをはさみながら、最後に、学生は本日の講義についての意見や感想を記入、提出しました。
|

(アイスブレークの様子)
|
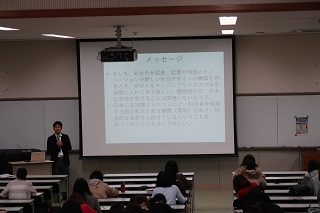
(竹原准教授から学生にメッセージを伝える様子)
|
平成31年1月29日(火)には、『なら学+』最終日として、南都経済研究所から振り返りと活動発表・総括講演が予定されております。
≪平成30年度 「なら学+」最終回 ~奈良に提案したいこと~≫

第15回 学生による事例報告 (1)十津川村での活動について (2)野迫川村での活動について
総括講演 南都経済研究所 吉村 謙一氏 「地方創生と社会人基礎力」
奈良女子大学で本年度開講されている『なら学+』では、これまで地域で活躍できる人材の育成をめざし、奈良県内の企業・自治体・大学・高専等からゲストスピーカーを招き、学生が奈良県の魅力を知り、奈良が抱える課題を見つめながら、地方創生について考えてきました。
平成31年1月29日(火)の最終回では、奈良県南部にある奈良女子大学サテライト施設(十津川村と野迫川村)を拠点とした学生の活動紹介を行い、それぞれに2組が事例報告を発表しました。
また、その後に「地方創生と社会人基礎力」と題して、一般財団法人 南都経済研究所 主任研究員 吉村 謙一氏による総括講演が行われました。
そして、専門的な立場からの提言も交え、受講学生は、この講義を通して得たものを振り返りました。

平成30年度 COC+政治・経済
平成30年度 地域と世界の文化論
平成30年度 社会科学特論
平成30年度 前期 地域社会技術特論