【8月6日】
第5回講義は、「はじめに実験を行いたいと思いますので、電気工学科棟3F 電気工学基礎実験室に移動いたします。」と、言う服部特命助教の一声から始まりました。
前半は、実験に先立ち、服部特命助教から"本日、主に何を取得するのか?"についての説明がありました。
|

(服部特命助教)
|

("本日、主に何を取得するのか?")
|

(回路基板を取り付けている様子)
|
①半導体デバイスのスイッチング特性
早速、回路基板を取り付けて、半導体スイッチの特性を測定する実験を行いました。ダブルパルス回路(実験)により、各班でターンオンとターンオフ時間が正しく測れたかの動作確認が行われました。
つぎに、"理想スイッチ"の説明をしたうえで、半導体スイッチでは色々な損出が発生することを述べ、それぞれの班でSi-MOSFETとSiC-MOSFET、Si-IGBTの3つのスイッチング損失を測定しました。そして、MATH機能の設定方法の確認を再度行い、(1)CH1とCH2の間にあるMATHボタンを押す。(2)信号源AをCH1、信号源BをCH2、操作を"*"(掛け算)に設定する。の手順で行いました。
|

(熱心に聴講する様子)
|

("理想スイッチ"の説明)
|
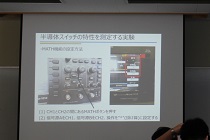
(MATH機能の設定方法の確認)
|
服部特命助教は、スイッチング損失を限りなくゼロに近づける"ソフトスイッチング"手法があることを電気学会の定義から抜粋して述べました。損失面だけを考えると、電流・電圧の重なりを小さくするために、高速スイッチングにすればよいが、ノイズやサージの原因となり、また、波形遷移時に大きな振動"リンギング" が発生することを学びました。そして、本日、最後の実験として"リンギング"の確認を行いました。
後半は、服部特命助教からバトンタッチして、石飛准教授による座学が開かれ、"これまでの確認"が行われました。
②モード解析法Ⅱ(中級編)
実際の各種スイッチング回路の動作を読む「モード解析法」の意義について、"新しい回路の導入"、"アプリケーションに合わせた改良"、"リンギング抑制対策"、"故障時の診断・解析&修理"の観点から示しました。その後、モード遷移図を用いて、モードがチェンジしたきっかけや転流理由などについて丁寧に説明されました。さらに、家電製品に多く使われているLLCコンバータのリンギング動作などについて詳しく説明しました。また、フルブリッジインバータとSEPPインバータ(SEPP:シングルエンデッドプッシュプル)の2タイプのインバータについてもそれぞれの特徴を説明されました。
(石飛准教授による座学)
③電力変換のメカニズム
石飛准教授は、「これまでのモード解析法Ⅱでは中級編として、回路の動作が読めるようになることを念頭に進めてきました。中級編と上級編との違いは、上級編では電力変換の仕組みと構造を知り、さらに深い部分の設計等にまで入っていき、実際にモノをつくってみる段階に移っていくことです。」と、述べられました。その上で、電力変換のメカニズムについて、世の中にある回路には、"電圧源には、電流源的デバイス"、"電流源には電圧源的デバイス"が回路の構成要素となっていることを伝え、受講者は実際に出力電圧が確認できるのかをパソコンでシミュレーションしました。
("パソコンでのシミュレーション"と"電力変換のメカニズムについての説明"の様子)
④高周波化による高性能化
本日の講座も最終段階に入り、石飛准教授から服部特命助教にさらなるバトンタッチが行われました。
(服部特命助教による座学)
服部特命助教は、回路の小型化について、スイッチング回路の体積を大きく占める部品である"インダクタ"、"キャパシタ"、"放熱器"を小さくすれば小型化につながることを述べ、スイッチング周波数を高くすることで、インダクタ、キャパシタが小型化される理由について説明し、高周波化により受動素子の小型化も可能であることを伝えました。また、損失を少なくすることで、放熱器が小型化される理由についても説明し、新材料デバイスの適用により冷却部の小型化も可能であることを示されました。回路の高効率・小型軽量化手法について、①低オン抵抗デバイス②高周波・高速スイッチング③ソフトスイッチング技術④多相化技術⑤磁気デバイス複合技術⑥制御技術⑦材料技術の7種類をあげ、「これらにより回路の高効率・小型軽量化が可能となる。」と、述べられました。第5回の講座もタイムリミットが近づき、ゲートブースト回路の紹介と高周波スイッチングの紹介、ソフトスイッチング技術の説明をして、滞りなく講座を終えることができました。
おわりに、服部特命助教は「お疲れ様でした!次回は、半導体デバイスの"スイッチング"のシミュレーションと"ミラー効果"について、もう少し詳しく説明して参りますので、宜しくお願いします。」と、結ばれました。
講義終了後には、真剣な眼差しで質問を行う受講者とそれに応える石飛准教授と服部特命助教の姿も見られ、この講座も半ばを迎え受講者と講師の信頼関係の深まりを感じるひと時となりました。